- 3月 14, 2025
- 5月 12, 2025
リウマチに関する血液検査のみかた
関節リウマチの診断や治療経過をみていく際には、血液検査の情報がとても大事です。
患者様ご自身でも検査結果の個別項目の意味を知り、自分の体の状態を正しく知っていただくと問題点を医師と共有しやすくなると思います。
体の状態を判断したり変化を知るためには、一つの項目だけに注目するのではなく、いくつかの項目のまとまりで総合的に判断したり、一回ではなく何度かの数値の変化に注目します。例えば肝機能であればAST、ALT、LDH、γGTPなどです。
少しの基準値オーバーでは心配しなくてもよい場合も多く、全体で意味をとらえることも大事です。

AST、ALT、LDH、γGTP
肝臓は薬の分解や排泄に関わります。薬の効きすぎや体に合わない場合に上昇します。特にメトトレキサートは効きすぎると肝機能障害が起きることがあります。脂肪肝や飲酒でも高くなります。

CRP, 血沈, MMP-3
CRP, 血沈は体全体の炎症を反映します。リウマチの勢いがある時や感染症で高くなります。リウマチの状態が落ち着いているのにCRPが高い場合は、どこかに感染症や腫瘍など炎症の原因が隠れていないか慎重に判断する必要があります。
MMP-3は関節炎の指標です。毎回の測定は認められていないため、3か月ごとなど間隔をおいて測定します。
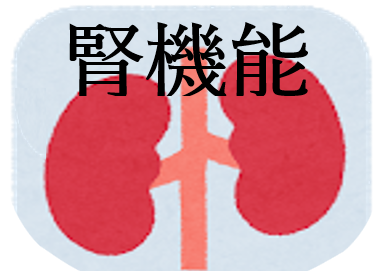
BUN(尿素窒素), Cr(クレアチン), eGFR(推算糸球体濾過量)
尿をつくる働きや脱水の有無をみます。尿から排出される薬を使う方は、特に注意が必要です。
電解質(ナトリウム(Na)、カリウム(K)、クロール(Cl)、カルシウム(Ca))は腎臓で調節されているため腎臓が悪いと乱れることがあります。
ナトリウム(Na)、カリウム(K)、クロール(Cl)は塩分バランスの指標です。特にむくみや心不全、高血圧の治療のために利尿薬を使用している場合は、ナトリウム、カリウムが下がりすぎていないか注意して観察し、下がりすぎている場合は調整が必要です。
カルシウム(Ca)は骨の状態と密接に関係します。骨粗鬆症の治療のためカルシウムのサプリやビタミンDを使用している方は、カルシウムの値を注意しておきましょう。カルシウムが高すぎると嘔気がでたり尿管結石ができやすくなるので高すぎるのも良くありません。その場合はカルシウムサプリやビタミンDの減量について主治医と相談しましょう。
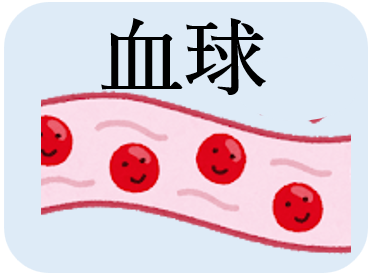
WBC(白血球)、Hb(ヘモグロビンまたは血色素)、Plt(血小板)
白血球は感染症のチェック、ヘモグロビンは貧血の程度、血小板は出血しやすさをみます。
メトトレキサートが効きすぎている場合に血球全般の低下が出ることがあります。
Hb低下は貧血を意味します。貧血イコール鉄分不足とは限りませんが、はっきりした出血のエピソードがない場合、わずかずつ消化管出血(胃、大腸の潰瘍や腫瘍)から、女性であれば子宮からの出血の可能性があります。貧血はビタミンB12、葉酸不足、腎機能障害、造血機能障害などでも生じます。
逆にHb上昇は多血といいます。多血の原因で多いのは、喫煙と睡眠時無呼吸症候群です。これらにより酸欠状態となるため、体は血を増やしてなんとかしようと反応して多血になるのです。
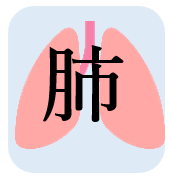
KL-6、LDH(乳酸脱水素酵素)
これらは間質性肺炎の指標です。上昇傾向の場合は要注意です。レントゲンやCTの画像を合わせて判断することが多いです。
LDHは間質性肺炎だけでなく肝臓や血液の異常でも上昇するため、ほかの項目とあわせた総合的な解釈が必要です。

HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)、血糖
HbA1cは1カ月間の平均血糖値の指標です。ステロイドを使うと血糖値があがりやすくなるため時々チェックします。すでに糖尿病の方では、良くなったかどうかの目安になります。
血糖値もHbA1cとセットで測定しますが、血糖値は食事の影響を受けてしまうため、採血前の食事の影響がないHbA1cはふだんの血糖状態を知るのに役立ちます。

コレステロール(HDL:善玉、LDL:悪玉)、中性脂肪(TG)
コレステロールや中性脂肪が高いと動脈硬化の原因となり、将来脳梗塞や心筋梗塞を起こしやすくなってしまいます。ステロイドの使用によりこれらの値が上がってしまうことがあるので時々チェックします。
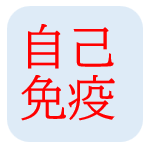
RF(リウマチ因子)
異常な免疫反応をみるものであり、リウマチの診断(リウマチらしさ)および勢いを反映します。リウマチ以外の膠原病や健康な人でも高齢になればなるほど、RFが陽性反応が出ることが多くあります。ただし症状がないのに健診でRFが高いと言われただけの場合は心配ないことが多いです。
抗CCP抗体
リウマチ反応のひとつです。診断の時に測定します。RFよりもリウマチに特化した指標で、関節の症状があり抗CCP抗体が陽性ならば、多くの場合関節リウマチと診断されます。また抗CCP抗体の値が高い場合は将来関節の変形が進みやすいため、しっかり治療していく必要があります。
(診断時や必要時に1回だけ調べます)
抗核抗体
膠原病を疑われたときに、様々な膠原病らしさがあるかどうか、最初に判断するために調べます。健康な方でも陽性になってしまうことがあり、膠原病らしい症状がなければ結果にこだわらない方がいい場合もあります。(診断時や必要時に1回だけ調べます)
陽性の場合、●●型という記載もついてきます。これにより、おおまかに疑い疾患が絞られます。
Homogenos型(均一型): 全身性エリテマトーデス、関節リウマチ、全身性強皮症(Nuclear型と一緒に)、シェーグレン症候群
Speckled型(斑紋型): 全身性エリテマトーデス、関節リウマチ、皮膚筋炎/多発性筋炎、混合性結合組織病、シェーグレン症候群
Peripheral型(辺縁型): PCNA様型:全身性エリテマトーデス
discrete speckled型(散在斑紋型): 全身性強皮症(限局皮膚硬化型)
nucleolar型(核小体型): 全身性強皮症、シェーグレン症候群
Cytoplasmic型(細胞質型): 原発性胆汁性胆管炎、皮膚筋炎/多発性筋炎、シェーグレン症候群、全身性エリテマトーデス、自己免疫性肝炎
核膜型またはgranular型(顆粒型): PBC、シェーグレン症候群、自己免疫性肝炎

B型肝炎関連(HBsAg・HBcAb・HBsAb・HBV-DNA定量)、HCV抗体
60歳以上の方だと、15%くらいの人が気づかない内にB型肝炎ウィルスに感染しています(当院調べ)。ほとんどの方は慢性肝炎にならずに「臨床的治癒」と呼ばれる状態になります。しかしB型肝炎に一度かかった人はわずかに肝臓内に潜伏してウィルスが残ってしまいます。免疫を抑える薬を使うと再発し重症の肝炎を起こすことがあり、免疫抑制療法を始めるときに検査し、感染既往と判明した方は再発していないかの監視のため定期検査が必要です。
HBsAg(HBs抗原):(+)の場合、B型肝炎ウィルスが現在増殖し血液中に存在していることを示します。
HBcAb(HBc抗体):(+)の場合、B型肝炎ウィルスに一度でも感染していることを意味します。現在ウィルスが増殖しているかはわかりません(増殖している場合としていない場合の両方がある)。
HBsAb(HBs抗体):(+)の場合、2つの可能性があります。B型肝炎ワクチンをうけていることによる(+)になる場合と、B型肝炎ワクチンの感染歴がある場合で。。ほかの検査との組み合わせと、ワクチンを受けたことがあるかどうかの経歴で判断します。
HBV-DNA定量:(+)の場合、B型肝炎ウィルスが現在増殖し血液中に存在していることを示します。B型肝炎ウィルスに感染していると、ウィルス量が多ければ多いほど肝炎が起きやすくなります。B型肝炎ウィルスが一度感染すると完全には体内から消失せず肝臓内に潜伏して残ります。免疫抑制療法を行うとまれにウィルスの再増殖が起きるため、感染既往者はHBV-DNAを定期的に測定し、再増殖がないかどうかを監視します。
HCV抗体:(+)の場合、C型肝炎ウィルスに感染したことがあることを示します。(+)の場合は現在の感染を示す以外に、C型肝炎の自然治癒や治療後にウィルスが消失していても、HCV抗体は陽性として残ります。
T-spot、クオンティフェロン(結核)
結核菌に感染したことがある場合は陽性となります。結核菌に感染したことがあってもきちんと治療して治した場合は問題ないのですが、気づかないうちに結核菌を取り込んでしまっている場合は免疫抑制療法により結核が本格的に発症してくる場合がありますので、治療開始の時点で結核菌に感染したことがあるかどうかを調べておくのが重要です。
結核の検査として有名なツベルクリン反応は、最近はあまり行いません。BCG(結核ワクチン)に対する反応と、実際の結核菌感染が区別しにくいこと、2度来院しなければならないこと、痛みが伴いやすいこと、定量的評価が難しいことなどが理由です。

わからないことや心配なことは、診察時に確認してくださいね。
